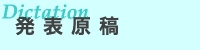法命題における意味と解釈
2000年3月11日 基礎法学研究会発表
はじめに
提出した助手論文の内容及び構成は、資料として配布した目次をご覧ください。本来の構成では、哲学的な基礎理論を考察したうえで法理論に関する分析を行なっているのですが、時間の関係と、またお集まりいただいている皆さんのご関心に合わせて、第2章である法解釈をめぐる議論の対立状況の解説を中心としてそれに必要がある限りで第1章の内容に言及していくという形をとりたいと思います。なお、発表中では敬称をすべて略させていただきます。
規約主義的描像とドゥオーキンの解答
本論文は、法解釈ないし法的判断ということの哲学的な位置付けを試みたものです。この問題をめぐる法哲学分野の業績としては井上達夫の「規範と法命題」があり、そこではタルスキの真理の対応説とカスタニェーダの規範理論を援用することで規範命題における真理値の存在が肯定されております。また、より近くはロナルド・ドゥオーキンとスタンリー・フィッシュのあいだ、あるいはフィッシュとオーウェン・フィスのあいだで論争が行なわれた点が記憶に新しいところです。しかしながら、視点をより広く取って言語哲学全体を見た場合、ソール・クリプキによって提起された規則のパラドックスをめぐって展開された問題系によってこれらの理論が共通して前提することがらに疑義が付されたと見ることができます。そこで第一にクリプキの法理論に対する影響を見定めることと、さらにその後の哲学的展開に沿って法理論における探究を進めることが必要である、これが本論文の問題意識であったと言うことができましょう。
まず最初に、法解釈とは何であるかという問題に対する、もっともシンプルな二つの回答から検討してみたいと思います。第一のものはいわゆる判決三段論法に表れているような、大前提に規則を規定している法文があり、小前提として事実認定をとることで、帰結としての命法が導かれるというものであります。概念法学であるとか、形式主義の試みというのは、このような数学的モデルとしての法をその極限まで推し進めようとしたものに他なりません。このモデルにおいては、法解釈の結果である帰結が我々に対して持つ規範的な効果の正当化は容易に行うことができます。なぜなら、大前提である法文は我々がこれに対して(フィクションであるにせよ)合意を与えたものであり、法解釈の過程は論理規則によって機械的に行われる以上、そこに解釈者の恣意的な判断が介入する余地はなく、従って合意による強制力を保存することができると考えられるからであります。このモデルを数学の公理系に関する議論との相似において捉えて、「限定的規約主義」(modified conventionalism)的なモデルと呼ぶことができるでありましょう。
第二の回答は、法は数学のように統一された体系を持っておらず、それを整合的に適用することは不可能だというものであります。その不可能性の淵源をどこに求めるか、すなわち法文自体の分裂的な性格に求めるのか、言語表現のあいまいさによる実質的な決定不全性に求めるのか、あるいは後述する論理的導出の不確定性に求めるかはともかく、このような立場からは法解釈が客観的に定まったものではない以上、それは主観的なもの、裁判官の思想信条の言い換えに過ぎないとされるでしょう。
言うまでもなく、これらのモデルは不十分なものであります。前者のモデルの問題は、法における解釈が持つ必然的な性格を説明することはできても、我々の多くが感じているその操作可能性については何ひとつ答えておりません。逆に後者は、確かに法解釈は完全に決定的なものではないかもしれないが、しかし何らかの必然性がそこに存在するという感覚を捉えることができません。オーウェン・フィスが主張する通り、「解釈とは完全に恣意的なものでも完全に機械的なものでもない活動である。それは読者とテキストとのダイナミックな相互作用であり、その相互作用の産物である。それは人間の経験の主観的・客観的次元の双方を作り出す活動なのだ」と言われなくてはならず、妥当な法理論にはこの両面を適切に説明できることが求められるでしょう。このための試みを、ロナルド・ドゥオーキンによる問題提起から明確に読み取ることができます。彼によれば、一般的に訴訟においては以下の三つの論点を区別して考えることができます。
第一に事実問題。これは現実の歴史的出来事をめぐる見解の相違ですが、我々はこの問題を検証によって解決する方法を知っています。第二に政治道徳と法への忠実性という規範的な問題。これについては、人々の間に意見の相違があっても何ら問題とされるには足りません。ドゥオーキンによれば、法的議論はこの二つの問題の中間に位置するものであります。そして、それがどのような議論であり、何についての見解の不一致であるのかを探ることが、法理論の中心的な課題と定義されるのであります。
ではこの問題に、ドゥオーキンはどのような解答を与えようとしたのでありましょうか。彼はその解答を「構成的解釈」と表現しております。ドゥオーキンによれば解釈とは常に、ある対象や実践がある目的のために行われたと想定することにより、それが属すると想定される実践形態や芸術ジャンルの最善のものとして提示することであります。ドゥオーキンは当初、解釈に会話的解釈・創造的解釈・科学的解釈の三類型を区分しますが、科学的探究は記述から目的概念を除去することを最終の目的としているとして、また会話的解釈もデビッドソンによる「善意の原理」(Principle of Charity)に現れているごとく、そこに存在する相手の意図を最善のものとする活動の一環であると主張することによって、最終的にはこれらの類型をすべて構成的解釈に一元化しております。要するにドゥオーキンにとっては、活動は常にある目的のもとに行われているものであり、従ってその目的を原理として把握することによって、前例の存在しない場合においても我々はそこで何が行われるかを知ることができるのであります。
このような構成的解釈を行うためのいわば材料としてドゥオーキンが想定したのが、今までの実践の結果であります。彼が構成的解釈の典型的な例として挙げている連作小説の企てにおいて、ある部分の作者は作品のそれまでの部分を参照しながら、そこに現れている目的を読み取り、それをより良い方向に表現するものとして自らの創作部分を付け足すのであります。この企てに携わる作者は、今までの作品を自らの視点によって読み取るのであり、決して機械的な規則の適用を行なうのではありません。しかし同時に彼は従来の作品を尊重する義務を負っているのであり、決して自由に創作を行なっているのではありません。ドゥオーキンによれば法的判断が持つ主観的かつ客観的な性質は、法がこのような作品としての性質を持っているからに他ならないのであります。
ドゥオーキン・フィッシュ論争
このようなドゥオーキンの理論に対する批判として、スタンリー・フィッシュによるものをまず取りあげましょう。周知の通りフィッシュは法学者ではなく文芸批評の専門家でありますが、ドゥオーキンが解釈をその議論の中心と据えたことから主にそれに対する反応を中心に法理論の問題にもコミットしております。さて、フィッシュの理論の中心は解釈戦略と解釈共同体という言葉で説明することができます。フィッシュによればあるテクストの意味はテクストの内部に存在するのではなく、特定の解釈戦略、すなわち何を目的として何を正しいとするかに関する理論からテクストを理解することによって供給されます。解釈戦略を共有する人々からなる解釈共同体は、それに属する個人の意味理解すなわち解釈の正誤を判定し、その内部において何がテクストの正しい意味とされるかを管理することになります。フィッシュによれば、意味はテクストそれ自体の性質ではなく、むしろ解釈共同体の所有物なのであります。
フィッシュの立場からは、ドゥオーキンの理論が自ら否定した二つの立場をともに含むものと規定されることになります。ドゥオーキンの枠組では第一に、既存のテクストが存在しない最初の一歩においては、それが拘束を受ける理由はありません。従ってこの時点の決定は完全に自由なものとならざるを得ないでしょう。第二に、テクストが蓄積されるに従って許される判断の幅は徐々に少なくなっていき、機械的なものとなっていきます。この二つの極はいずれも、法的なものではないとしてドゥオーキンが排除したがった当のものに他なりません。
フィッシュはこれに対し、解釈は常に自由なものであり同時に束縛されているという議論を展開します。彼によれば、第一にある解釈戦略を前提した場合その正誤は解釈共同体によって判定されることができ、従って解釈はこの意味では完全に機械的なものです。しかし第二に、いかなる解釈戦略が許容されるかはテキスト自体からは定まりません。我々はどのような解釈共同体に属することも自由であり、従って、いかなる結果を得るかは自由であるということができます。フィッシュにとって、あるテクストは常に前提された解釈戦略によって意味を与えられているものであります。我々は常に解釈戦略の中からテクストを見るのであり、従って意味を担っていないような、意味から中立なテクストないし認識は存在しません。
二つのパラドックスと解釈への影響
ドゥオーキンとフィッシュの間で行われているこの論争の、いわば基盤に疑いを突きつけるのが、ソール・クリプキによって提起された「規則のパラドックス」とルイス・キャロルによる「アキレスと亀のパラドックス」であります。この二つのパラドックスの詳細な記述についてはレジュメの別紙をご覧ください。簡単に結論だけを述べれば、もしこのパラドックスが正しければ、我々は自分もしくは第三者がある規則に従っているということを検証するための事実を決して手にできないことになります。もちろんこれは受け入れがたい結論であり、この二つの議論をパラドックスであると述べることは当然ながらそのような価値判断を前提としております。しかし第一に、パラドックスの論理的な構成が誤っている(例えばそこに単純な論理演算のミス)という主張がなされたことはありません。第二に、パラドックスの射程を抑えることによっていわば無毒化を図るという試みも(ここでは詳述を避けますが)失敗に終わっております。従って以下では、パラドックスの表面的な帰結、すなわち、ある規則が何を許し何を許していないかを規則に関する事実のみから知ることはできないという導出の不確定性を肯定したうえで議論を進めたいと思います。
では、導出の不確定性を認めることからどのような議論が行われ得るでしょうか。通常対立的なものと考えられているドゥオーキンとフィッシュの理論ですが、この問題に関してはは両者の間に大きな共通性があるということを指摘しなくてはなりません。
まずドゥオーキンについては、彼の用いている解釈という言葉に二つの局面があることに注意しなければなりません。それは第一に、過去の実践から対象のもつ目的を原理として把握しようとする行為であり、ここでは目的構成的解釈と呼ぶことにしましょう。第二は、参照可能な法源(制定法、判例に加え、ドゥオーキンではここに原理が加わります)を大前提として、小前提たる事実認定とともに推論を行い、帰結たる判決を得る過程であります。我々が当初、限定的規約主義の描像における解釈ということで意味していたのはこの局面でありました。これを適用における解釈と呼んでおきましょう。ドゥオーキンが法実証主義に対して加えた批判は、それが法の欠缺、すなわち参照すべき法が尽きる可能性を認めていたことを中心とするものでした。これに対してドゥオーキンは目的構成的解釈によれば法の欠缺は存在しないことを主張したのであり、言い換えれば、適用における解釈の局面においては法実証主義と変わるところはありません。このことは、歴史と慣例によって十分に意味が確定しているルールにおいてはそのルールが何を命じているかは明確であると彼がしていることにも現われています。
これに対しフィッシュはある事例における帰結が複数あり得ることを認めており、一見導出の不確定性を肯定しているように見えます。しかしながら、彼の解釈共同体理論は導出が確定的であることを前提にしてはじめて成立するものに他なりません。なぜなら彼にとって、解釈共同体の存在はあるテキストにおいて行われた解釈の帰結の相違から理論的に想定されるものとなっているからであります。もし解釈戦略とテキストから行われる導出が不確定なものであるならば、たとえその結果が散乱したとしても解釈戦略の複数性をそこから導き出すことはできないはずであり、従って、複数の解釈戦略の存在を論理的に措定するタイプの議論は導出の不確定性と両立不可能であります。
いずれにせよここで指摘しておきたいのは、この両者の議論があくまで論理的な導出の必然性を前提として組み立てられているものであり、この問題に対する対処を組み込んでいないということであります。従って議論の必然性という問題においてはクリプキ以前の段階に留まっているということが言え、たとえその結論を救いたいとしてもその立証のための道具立てはより洗練される必要があると言わなくてはなりません。
クリプキの懐疑的解決と法理論への応用
では、クリプキ自身はこのパラドックスにいかなる解決を与えることによって導出の必然性を救出しようとしているのでありましょうか。この問題に対するクリプキ自身の解決は、「懐疑的解決」と呼ばれております。それは、「意味を理解しているから、言葉を正しく使う」という構図を、「言葉を正しく使っていなければ、意味を理解していない」という対偶の形に転倒することをその中心に置いています。クリプキによれば、ある推論が正しいとされるのはそれが真となるような何らかの条件(真理条件)に対応しているからではなく、その問題に対して共同体が与えるであろう反応と一致していることによるのであります。すなわちここにおいて、正しさはある共同体においてその言明を為すことがどのような場合に許されるかという言明可能性条件もしくは主張可能性条件の水準に移行することになります。
クリプキの結論を法理論に忠実に適用しているのが、チャールズ・ヤブロンであります。ヤブロンによれば、導出の不確定性の問題を解決するために我々は法命題においてもクリプキの懐疑的解決を受け入れ、命題の真偽を真理条件によってではなく、主張可能性条件に転換すべきなのであります。彼によれば、例えば分離教育システムを維持している都市が憲法第14修正に従っているという言明が否定されるのは、ルールのテキストと個々の反応のあいだの関係によるのではなく、テキストを構成する言葉が私の属する共同体の言語において、すなわちその生活形式において演じる役割に関する知識によるのであります。ここから彼は、法命題は適切な文脈において・適切な主体が用いることによって、かつそのことによってのみ真と主張され得るのであって、法文の意味を決定する「最上級の事実」は存在しないと主張しています。彼によれば、そのような事実、例えば立法者の意図が存在したとしても、それによって我々の行動に何らかの拘束が加えられることはありません。従って、それを論じることには実質的な意義が存在しないのであります。
では我々がある反応において一致しているということはいかに知られるのでありましょうか。ヤブロンにとって、外形的な行動において我々が一致することは「ナマの経験的事実」(brute empirical fact)であり正当化を必要としない事柄であります。我々の規則における遂行は、理論的には不確定ですが因果的には確定的である、すなわち、十分に有能な決定者であれば、特定のケースにおける反応としてそのルールの正しい適用に至ることができるようなものであると彼は述べています。だが、実際に意見の違いが存在しているではないかという反論があり得るでしょう。彼によればそれはある種の問題、たとえば「鯨は魚だろうか」というような問題においては社会における合意が完全なものではないという事実の反映であるに過ぎません。そして法は、適切な状況で・適切な主体によってなされるという真の主張可能性条件を満たす裁判官の宣告という手段により、社会における「適切と思われる使用」を変更するという活動であります。法は、何が正しいかに関する社会のチェック基準を明示的に変更する手段を持っているという意味で特殊な制度であり、従って重要なのは、現存する法的言語のありようを全体的な言語との関係で把握するとともに、その共通理解を改変するメカニズムとしての法的論証を研究することである。これがヤブロンの結論であります。
デニス・パターソンによるポストモダン法理論の提唱も同様の試みと理解することができます。パターソンは、モダニズムの性格を認識論における真理条件をめぐる問題と定位したうえで、ポストモダニズムの企てを主張可能性条件への移行として捉えています。そこでパターソンは、フィリップ・ボビットの様式理論を引用し、法命題が真であるのは、法的論証のいくつかの様式、すなわち歴史的、教義的、衡量的といった論証の方法に合致することによって、かつその時に限ってであると主張しています。ボビットによれば、法命題の正誤はこれらの様式のいずれに従っているかという基準でしか判断することができません。正義にかなっているかを決めることはこの正当化の外部にある規準であって、従って人は法的論証の帰結を評価することができますが、正義の観点から論証の成否を決めることはできないのであります。パターソンはこの結論を利用し、法全体を様式によって構成される論証の実践であると捉えています。
クリプキの懐疑的解決の問題
さて、このように応用されるクリプキの懐疑的解決に対しては、多くの論者が批判を加えています。ここではそのうち、一致に関する問題に焦点を絞りましょう。例えば2+3が真であると主張することができるのは、私が与える解と共同体が与える解がともに5であり、そこにおいて一致しているからであるというのがクリプキの主張でありました。しかし、導出の不確定性を徹底するならば、そこにおいて何によって一致しているということが主張できるのかと問う懐疑論者を想定しなくてはなりません。この問題に対し、クリプキはどのように答えることが可能でしょうか。
例えば57+68のようなやや複雑な計算において、我々はそれが導出される過程を数字のケタ表現や繰り上がりといった概念に訴えて説明することができます。しかしその計算に理由を与えるゲームの基礎にある単純な——6+7といった——ことがらに関しては、我々は自分がそのように確信していると言うだけで主張することが許されるというのがクリプキの解答であります。それはあらゆる論証、すなわち問いと答えからなる言語ゲームの基礎を与える、いわば「河床」(bedrock)なのであります。これを後期ウィトゲンシュタインの用語から「生活
形式」(form of life)と呼ぶことができるでしょう。我々の論証は、疑い得ないものとしての生活形式の一致を前提として行なわれる営為として定位されることになります。ここで注意しなくてはならないのは、このような生活形式は決して言語によって描写されることはないということあり、何故ならそれは、ルールとして記述すればそのことによって直ちにそれは導出の不確定性の対象になるからであります。ここに我々は、言わば「不可視の基礎付け主義」(invisible foundationarism)の姿を見出すことができるでしょう。そして今までに説明した
個々の理論はすべて、このような不可視の基礎付け主義の構造を持っているというのが私の主張であります。
フィッシュの解釈共同体理論からこの構造を説明しましょう。解釈戦略によってテクストの意味が異なって与えられることを肯定しつつ、我々は複数の意味から何を良いものとして選びとるかに関する規準としての「規律的ルール」を導入することができると主張するオーウェン・フィスに対し、フィッシュは一貫してそのようなルールの導入を拒否しております。それはフィッシュにとって、書かれたルールはそれ自体テクストであり解釈を免れないもの、すなわち基礎たり得ないものであるからに他なりません。従って彼は論証の正しさの基礎を書かれたルールの存在しない、本能的・反射的地平に求めざるを得ないのであります。そこにおいてルール適用を教育する過程とは反射的に正しい反応ができるようにするという意味での訓練でしかあり得ず、言語を含むあらゆる規則準拠は——例えば水泳と同様の——実践的知識と定位されることになるでしょう。ですがこのことを、例えば大学で行なわれている法学教育と照らし合わせるならば、この理論が持つ問題点は明らかであるように思われます。
既存の理論の問題点
さて、これらの理論についてどのような評価を加えるべきなのでしょうか。ここでまず、それらを大きく二つの区分として理解することが有用であると思われます。
それは第一に、導出の確定性を前提として、帰結の複数性を解釈戦略や「目的」の複数性から説明する試みであり、私はドゥオーキンとフィッシュの理論をこの区分に含めて「解釈理論」と呼んでおります。それはこれらの理論が、法文の意味を知るためには常に解釈が必要となるとともに、それによって正しい解を得ることができることを保障しているからであります。
一方第二に、導出の不確定性を前提に真理条件説を放棄する理論があります。ヤブロンとパターソンはこの類型であり、私はこれを「実践理論」と呼んでおります。彼らによれば法命題は適切な時に・適切な主体によって遂行されることによって、かつそのことによってのみ真である(あるいは、真と主張され得る)のであります。逆に言えば、彼らにとって法命題の真偽を論ずるのに必要なのは人々の法実践に関する観察のみであって、意味や解釈といったテキスト自体に関する議論を行うことは無意味ないし有害だと言うことができます。
これらが個々に抱える問題点については既に若干の考察を行ないましたが、ここでは共通の問題として、これらが裁判ないし法実務において重要な諸特徴を説明できない点を挙げたいと思います。
第一の問題は、対審構造の必要性であります。言うまでもなく、我々の社会における裁判は双方当事者の主張をもとに裁判官が判断を加えるという構造を基本としております。そこにおいて当事者があくまで対抗的な立場に立つものであるということ、またこの対審構造を義務的に維持することが求められることがあるということは、他の紛争解決手段においては基本的に見られない裁判に固有の特徴だということができるでしょう。従って、法解釈に関する議論は対審構造の存在と意義を適切に説明できる必要があると考えます。
しかしながら私の考えるところでは、ドゥオーキンとフィッシュの解釈理論はともにこの点の説明に失敗いたします。第一にドゥオーキンの構成的解釈理論については、そこにおける裁判官の独話的性格が早くから指摘されておりました。理想の裁判官たるヘラクレスは、過去の実践を元に自ら目的構成的解釈を行い、自ら適用における解釈を行なうのです。もちろんこの性格はヘラクレスが規制理念としての、理想的な裁判官の判断として想定されていることに部分的にはよるでしょう。ここから植木一幹はハーバマスの議論を引用し、ヘラクレスの行なう解釈を目的と手段を共有する会話的共同体のものとして考えることが重要であると指摘しています。確かに裁判官の合議体としての法廷をそのようなものとして考えることは可能でしょう。しかしながら、対審構造において裁判官と両弁護人は疑似的な敵対関係とその審判者の位置に立つのであって、目的を共有しないと考えることがむしろ適当でありましょう。両当事者は互いに自らの立場を正当化しようとするのであって、最善の解決を自ら得るために努力するわけではありません。すべての参加者が目的と手段を共有する対話的共同体に属するのであれば、例えば国選弁護制度の必要性などなく、裁判官と検事の努力によって最善の解決を得ることができるでしょう。
一方フィッシュの解釈共同体論については、オーウェン・フィスが指摘する通り、裁判官はほとんど本能的に、あらかじめ内面化された解釈戦略に従って解釈行為を行うとされております。フィスはここで、このようなモデルが現実の裁判の実態を捉えていない、すなわち両当事者の提示し合う解釈からより良いものを選ぶ裁判官の選択という行為をとらえていないと批判するのですが、同時にここでは対審構造の意味がまったく失われていることに注目するべきでしょう。裁判官・弁護士あるいは検事は法という解釈共同体のメンバーであり、だとすれば彼らの導く結論は本能的・反射的なレベルにおいて一致するはずであります。ここで、それぞれの役割が解釈共同体なのであり、彼らは別々のサブコミュニティに属しているという考え方もなお可能でしょう。しかしこの場合、それは個々の解釈共同体の実態を説明することはできても、その事実を正当化する力はないことにな
ります。
これに対しパターソンやヤブロンの実践理論からは、対審構造の必要性は明らかであり、それは現に両当事者が何を望むかにおいて対立している点に求められます。例えばヤブロンにとって、根本的に存在するのは両弁護人の「わが方の当事者を勝たせろ」という主張のみであり、法的議論はその言い換えに過ぎません。そして、なぜその弁護人がその主張すべきかは社会的に期待されている役割によって決まっているのであります。
しかしながらこの場合、第一に理解できないのは裁判において我々が争点を構成することであります。裁判における弁論は、その立場の違いにもかかわらず共通の議論の基盤を形成することから始まると考えることができます。また、たとえ事実認定について相手の主張を取ったとしても別の主張ができるという予備的議論を行うのはむしろ当然の弁論であるということができます。対審構造とは単純な対立ではなく、何を争わないか、何が一致しているかということを確認したうえでどのような導出が許されるかを主張し合うものだということができるでしょう。
第二に、実際に主張していることが「わが方の当事者を勝たせろ」のみであるなら、なぜそれを直接表現しないのでしょうか。ヤブロンはこの点について、そこで弁護士が「私は望む」という形で表現することを誰も期待していないこと、換言すれば、そのような言葉遣いが法的論証の規約によって非常に弱いものとされることがその原因であるとしています。つまりこの点に関してヤブロンはそれは規約であると答えるしか方法がないということなのであり、不可視の基礎付け主義の構造がここでも繰り返されているということができましょう。
第三に、ある法的主張が意図の言い換えになることの理由をここから説明することはできません。確かに両弁護人の目的は自分の代理する当事者が勝訴することにあると言ってもよいでしょう。しかしそのことは具体的な議論とその目的との関係を何ら保証することになりません。「このスピーチは憲法第1修正によって保護されている」と言うことと、「このスピーチは合衆国政府によって検閲されたり抑圧されるべきではない」と言うことのあいだに差がないとヤブロンは主張していますが、そのことはいったいどのように正当化することができるのでしょうか。こういった言明の組すべてについて言語ゲームの規則に訴えるならそれは無限の規則を含むことになるでしょう。しかしそれこそがクリプキの拒否した描像であったと言うことができます。
不可視の基礎付け主義は、我々のルール適用の正当性を、究極的には本能的・反射的な反応に求めることになります。しかしこれは、我々が一致しているという事実の説明にはなりますが、それが正当であることの立証には失敗していると評価されるべきであります。例えばある落語を聞くと我々が全員笑い出すという場合、我々が本能的・反射的にそのような傾向を有していると述べることは正しいかもしれません。しかしそこからは、我々が笑うことが正しく、笑わないことは誤りであるという正誤の次元に関する主張は何一つ導かれ得ないのであります。では、我々はどのようにしてこれらの事柄に関する語りを回復することができるのでしょうか。私はここで、それは以下の三つの議論、すなわち無限定的懐疑論・根元的規約主義・正当性に関するデカルト的地平批判を組み合わせることによって可能だという主張を展開したいと考えます。順に説明を加えましょう。
二つの懐疑論
まず第一に我々は、懐疑論の二つの形態を慎重に区別しなくてはなりません。その第一の類型は「すべてを同時に疑うことができる」というものであり、これを「全面的懐疑論」と呼んでおきましょう。これに対し、「すべては疑いの対象になり得る」とする類型を考えることができます。後者は、ある命題に対しそれを疑うことができる立場が必ず存在することを主張していますが、それがある一つの立場であることを主張しません。この立場を「無限定的懐疑論」と呼びましょう。全面的懐疑論に対しては、主に相対主義との内的関連性を中心に多くの批判が加えられています。例えば井上達夫のように、その立場が自己論駁的であることを主張してもよいでしょう。これに対し、生活形式を疑い得ないもの、解釈にあたるに先立って予め与えられた記述し得ないものとする考え方——すなわち不可視の基礎付け主義は、この無限定的懐疑論を否定する議論であります。そこでは解釈共同体の権威なり、我々の実践の圧倒的な一致なりが疑い得ないものとして想定されております。しかしそこで彼らが採用できない立場として想定しているのは全面的懐疑論のみであり、何も疑いから免れてはいないが、ある問いを発するときにそこで問われていないことが前提として扱われ、問いから免れるということを中心として構成される無限定的懐疑論については論じられておりません。むしろここから、彼らはこの二つの立場の差異を理解していなかったからこそ、ある事柄を疑い得ないものと定位することによって懐疑から逃避したのであると論じることができると思われます。
それでは、無限定的懐疑論はいかにして擁護することが可能でありましょうか。生活形式の一致に基礎を求める不可視の基礎付け主義においては、ある種の枠組、すなわち一人称感覚命題や単純な数学的命題についてそれは枠組に属する命題であり疑うことができないものである、それに関する論証ができないようなものであると定位されているということができます。このことを例えば数学的命題について考えてみましょう。通常の言語ゲームにおいては、例えば2+3=5が証明として規範的に機能します。それは、この命題が他の経験命題(例えば豆2粒と3粒を一つの山にまとめると5粒になる)に対して真理値を帰属させる基準となるという形で現れます。このとき、例えば4粒しかなかったという帰結が生じた場合には、経験命題の側がさらなる検証にさらされるか、どうしても解決できない場合には「何かの間違いだったのだろう」という形で棄却されることになるでしょう。懐疑にさらされるのは経験命題の側であって、数学的な命題ではありません。そしてここで枠組として用いられる命題については、それに向けられた疑いに対して「だってそうじゃないか」、すなわち信じることをそのままに主張することしかできないというのがクリプキの主張でありました。言い換えれば、そこではいかなる検証も行われ得ないことが懐疑的解決の前提となっております。
しかし、2+3=5において我々は、例えばリンゴ2個と3個の山を作り、両方合わせると5個になるではないかと主張することがあり得るでしょう。そのような場面を、特に子供に対する規則の教示の場面において想定することは難しくありません。ここでは数学的な命題に対して経験命題がその真偽を与えるような関係が成立しています。このとき経験命題は疑われることなく、それ自身が数学的命題の探究への枠組となっているのであります。枠組である命題が検証されるとき規範的機能の関係は逆転します。このようにして我々は、複数の言語ゲームにおいて枠組となる存在が入れ替わることを想定することができるのです。
根元的規約主義
第二に私は、野矢茂樹による根元的規約主義の試みを紹介すべきであると考えます。限定的規約主義の問題点は、有限の公理と推論規則から無数の定理を導出すること、すなわち直接的規約と派生的規約の区別を想定することによって、その導出を不確定なものだと主張する可能性が存在する点に求められます。この問題に答えるために想定される一つの立場が、「根元的規約主義」(radical conventionalism)です。直接的規約と派生的規約の区別を維持することを断念し、すべてを直接的規約と見倣す。あらゆる規範性は先立つ規約から派生したものではなく、まさにそこにおいて取り決められた規約に他ならないと考えることがこの立場の中心であります。しかしこの定式化は直ちに、すべてがその場における規約の結果であるとするなら論証という行為がいかなる意味を持つのかという批判にさらされることになるでしょう。ある命題から別の命題が帰結するという論証を行うとき、我々は、前提となる命題を認めながら帰結となる命題を認めないことはあり得ないということを主張していたのでありました。もし導出の必然性が存在しないのなら、論証は公理を必然的に展開していくという作業ではあり得ないことになります。
野矢はこれに対し、根元的規約主義の描像においては論証は意味を発見する道具となると述べています。クリプキが問題視した考え方をもう一度参照しましょう。「もし意味を理解しているなら、彼は言語を正しく使う」。導出の不確定性によって、意味を理解しているという事柄が理解不能になりました。根元的規約主義においては、言語を使うことによって意味が制作されると考えることにより、この問題を逃れようとするのであります。ある命題からある命題が必然的に導出されると述べることは、第一にそのような関係を規約としてその場で制作することであり、それによって前提となる命題の意味を定める行為なのであります。論理とは、何か外部にある真実を発見するための手段ではなく、我々の実践を必然性によって記述し、かつそのことにおいて、さきほど命題の検証において述べたような規範的構造を作る手段なのであります。
ここから例えば、数学的命題が必然的であるとされるのは、それがさまざまな場面で経験的探究の枠組として利用されるという我々の活動によって形作られた事態であり、命題自体の性質によるものではないという帰結が導かれます。命題の規範性は、それを我々の行為、実践を規制するものとして捉える我々の認識によって形成されるのであります。
正当性に関するデカルト的地平批判
さて、以上のような定式化が説得的であるかとは別の問題として、しかし我々はそのような規約を行なっていないという反論を考えなくてはなりません。野矢はこれに対し、それは社会契約説に対して規約行為の不在を言い立てることと同じであると主張しています。そこにおいて契約や規約は歴史的事実の指摘ではなく、事態の説明のために用いられた補助線のようなものであります。しかしここから、規約の二つの性質を読み取ることができるでしょう。第一に、確かに我々は取り決めを行なっていません。我々が規則に従って行動するときはたいてい盲目的であります。第二に、導出の不確定性を前提にする限り、規約はわれわれの未来を拘束するものではなく、一定の事柄が起きた後で振り返ってその存在を見いだすようなものでしかあり得ません。このことに関する説明が、根元的規約主義には求められるでしょう。
また前述した無限定的懐疑論に立つ場合、我々はある前提においてしか疑いのゲームを行なうことができないということになります。しかしそれでは結局、そのようにして展開されたすべての論証の体系に対して根拠を与えることはできないのではないかという疑問があろうかと思います。この点に対する説明が、無限定的懐疑論には求められるでしょう。
そこで第三の議論として、デカルト的地平をめぐる問題に注目しようと思います。J. L. オースティンは、「本当の」という言葉について「否定主導語」(trouser-word) という分析を行なっています。一般的な言葉がある性質の表現であって、例えば「赤くない」という否定後の役割はその欠如、すなわち消極的な意味を表現するに過ぎないのに対し、否定主導語の場合は否定語の方がむしろ性質の共通性を担うことになる。このことは例えば、本当のなになに、本当のこれこれといったものに共通の特徴が存在しないことに示されています。オースティンによれば、「本当の」という言葉の機能は、何かを肯定的に特徴づけることではなく、本当でない可能なあり方を排除することにあるのであります。
野矢茂樹は、外界の事物の実在性に関しても同様に否定的契機の働きが逆転していると指摘しています。我々は認識における正常な状態に共通する何かを把握しているのではなく、むしろ知覚におけるさまざまな異常が存在しないときに、それを実在とみなしているのであります。従って野矢によれば、「懐疑に焼き尽くされた焦土から、根拠づけられたもののみが徐々に立ち上がってくる、このデカルト的イメージはいささかも実情ではなく、また実情ではありえない」。ここに表現されている問題設定を「デカルト的地平」と呼んでおきましょう。そこにおいて、我々の探究の及んでいないすべての事柄は、何らかの意味で偽であります。しかし、我々が正当性を証したもののみがそこで真なるものとしての存在を許されるというこのデカルト的地平の問題設定自体は、すでにそこで疑いを免れたものとされていることに注意しなければなりません。井上達夫の相対主義に対する批判と同様、このデカルト的地平の想定も超越的にして自己論駁的な主張として我々は却下しなければならないのであります。
また、我々は規則をめぐる問題についてもこのデカルト的地平批判を遂行しなければなりません。我々が説明したかったのは、普通の場合において我々は盲目的に規則に従っているということでありました。そこにおいて、規則はゲームの進行において透明なものとなっているのであります。ここで規則遂行に何らかの齟齬が生じることを、大森荘蔵の表現を借りて「よどみ」と呼びましょう。我々が認識するのは、さまざまなよどみの共通性であり、よどみの存在しない、正常な規則遂行の共通性ではありません。そして重要なのは、通常の規則遂行において前提とされている規則の意味、すなわちその規則が何を命じており何を命じていないかをめぐる議論が行われるのは、その問題に関する争いが生じた場合であり、かつそのときのみであるということであります。
論証という行為、すなわちある命題の意味を制作することは、規則をめぐる遂行がよどんだときに、そのよどみを解消する手段として命題の必然性に訴えることにより発生します。ある遂行に同意しないものが現れ、規則の遂行がよどんだとき、私は論証によって前提となる命題の意味を制作し、それが規範的なものだと主張することによって異論者を同意させようと試みることができます。相手が同意し、遂行がよどみのない状態に戻ったとき、振り返ればそこに意味があり、ある規則に従う我々が存在したかのように見えるでしょう。いわばそこで意味は、直接に知られることなく、導出を基礎づけるものとして想定される理論的存在なのであります。
私が行為する瞬間において、それはあくまで根拠を持たない行為であり、暗闇の中の跳躍に過ぎないと言われるべきであります。私の行為に対して周囲の人々が異議を唱えず、そこによどみが発生しないとき、あえて言うとすればそこに規約が存在したのだということになるでしょう。しかし、規約が存在したことはよどみが発生しなかったことによって否定主導的に示されるしかありません。根元的規約主義の中心にある概念を、このように賭けとしての行為と黙示的な承認として捉えることができると思われます。
意味の制作理論
以上で説明した三つの立場の複合によって定位される立場を、「意味の制作理論」と呼ぶことにしましょう。では、意味の制作理論の観点から今までに取り上げたいくつかの法理論の問題点についていかなる代案の提示が可能になるでしょうか。まず法の適用ということにおいて、裁判のような争いが生じている場合のみを考えることは正しくありません。むしろ、我々の日常生活はよどみのない法適用に満たされていると考えることができます。そこにおいて我々は自然に・盲目的に規則を認識しているのであり、だからこそ盲目的に規則に従い、あるいは規則に反することができるのであります。このような場面において解釈は登場しません。
一方、法の命ずるところに関する十分な一致が得られなかった場合に行われるのが法解釈であります。そこにおいて我々は、互いの行為を正当化するような意味連関を提示し合うことになりますが、このとき探究の枠組として争われない地平を設定することなしには、枠組との連関によって示される必然性という概念が意味をもたなくなるでしょう。従って法的論証は、争わない枠組を定めての営為である必要があります。これらの点から、法の謙抑性が形作られます。法解釈はあくまでよどみの解消に行われることなのであり、それを超えることはできません。
導出の不確定性において示されているのは、何ごとか法文の中に存在する意味が流れ出すことによって我々が意味を認識するという描像は棄却されなければならないということであります。そうではなく、我々がある法文を根拠として特定の帰結の正当化を試みるとき、それはその法文の意味がその帰結を含むように理解されるべきだという主張が行われているのであります。規則遂行のよどみにおいて行われた多くの解釈はそれぞれに前提とされた命題と帰結のあいだの意味連関を作り出しています。われわれはそれらをさらに互いに関連させていくような記述を行うことによって、さまざまな既存の命題群を統一的な意味連関の下に置くことを試みることができます。これが解釈の目的だということができるでしょう。
しかしなぜそのような解釈を行なわなくてはならないのでしょうか。我々はよどみを解消していくことによって、とりあえず意味の理解に関する一致を得ることができます。しかし、導出の不確定性が存在する以上、ある一致は次の一致を保証しません。従ってせいぜい、ある一致は次の行為によって河床として、とりあえず疑われることのない枠組としての地位を得ることしかできないでしょう。だとすればそれは無益な行為であり、行なう必要のないものであるかのように思えます。しかしその一方で、よどみの拡大を放置すれば我々の一致は失われ、規範の必然性や同じように振る舞う我々といった存在が失われることに注意しなくてはなりません。導出が不確定である以上、我々の実践は常に散乱と崩壊の危険にさらされています。論証を通じてある振る舞いの仕方を人々の共通のパターンとしていくという営為を続けること、言い換えれば絶え間ない解釈とコミュニケーションだけが、我々の盲目的な規約遂行たる社会の実践をかろうじて維持する手段なのであります。
解釈ということ、法ということ
以上で主張されたことを要約するならば、次のようになります。第一に、解釈ないし論証は規則に関する遂行に何らかのよどみが生じたときにのみ要請されることであり、従って意味もそのような場においてしか存在しません。第二に解釈とは、ある命題が必然的に別の命題を含むと定位することによってよどみを解消しようとすることであり、そこでは前提とされた命題の意味が制作されていると言うことができます。意味は、前提とされた命題が主張された時点に遡って存在していたものとして、解釈の時点で制作されるのです。解釈によって命題に意味が付与されることから、これを「物語り」(narrative)と定位することができるでしょう。論証の必然性をめぐる言語ゲームにおいてはある命題と別の命題の規範性に関する物語り、すなわち規範物語りが制作されるのであります。この規範物語りの制作にあたって、解釈によって意味がいわば過去に投げ込まれるために、我々は解釈に先立って命題の意味が存在していたのであり、それを突き止めることが解釈であるかのように考えてしまうのですが、それは誤解に過ぎません。第三に解釈とは絶えず崩壊と散乱の危機にさらされている我々の実践を、相互コミュニケーション可能なレベルに維持し続けるために要請される、終わりのない企てであると言うことができます。
しかしここで我々は、最初の問題に戻ってしまうことになるでしょう。第一に、意味の制作理論においては、事実命題と規範命題の差はよどみを解消する際にどちらが安定的なものと見做されるかという位置にのみあるのであり、形式的ないし本質的な差は存在しないと言うことができます。とすれば、当然ながらその両者のあいだに存在するとされていた法命題の位置も失われることになるでしょう。第二に解釈とは何かという問題に対しては、意味連関を制作するとともに前提とされた命題に規範的な地位を与える行為だと述べることになるのですが、これは解釈一般に対して述べられた事柄であり、法解釈の独自性はそこから失われていることになります。では我々は法解釈が例えば文学作品の解釈と違う点をどこに見出すべきなのでしょうか。
ここで、ボビットの様式理論において特定の基礎付けの形式、例えば「私はそちらを望むから」「ただなんとなく」といったものが排除されていることに注目すべきであると考えます。ヤブロンやパターソンにとって、様式が特定のものに限定されているのは言語的規約の実相であり、批判的吟味の対象とならないものでした。しかし、法的言語が全体的な言語に対して持つ位置を問題にするのであれば、そのあいだに共通するものよりも相違点の方に目を向けることの方が示唆に富むように思われます。そしてここでは、日常的な言語使用においては行為の基礎付けとして(少なくともある程度)許容されるこれらの様式が当然のように失われていることを問題にする必要があると考えます。
野矢茂樹は行為の見方に一人称的なものと三人称的なものの双方があることを指摘しています。意図的な行為においては、本人が何を望んでいるかということが重要な判断の観点であり、ここから成功・失敗に関する関心が必要とされます。一方、意図せざる行為、すなわち「君が気付いていないかもしれないが、なになにしたのだ」という表現の対象となるような行為においては、当然のことながら本人の意図という一人称的な観点ではなく、何をしたことになっているのかという三人称的観点においてのみ特定の行為が評価されます。野矢はこの点から、一人称的観点の目的が理解にあるのに対し、三人称的観点は裁きのためのものであるとおおまかに述べています。言い換えればそれは、行為の客観的な帰結評価を試みるものであると言うことができるでしょう。
ここで一般的な意図の表現において一人称の特権が存在することに注目しましょう。例えば「コーヒーを飲もう」と言いながらそれに向けた行動をとらない人を我々が了解できないのは、その意図の表明をとりあえず探究の枠組として、正しいものとして受け入れているからに他なりません。一方、法の関与する場における意図の表明は、そのように一人称特権があるものではないと言うことができるでしょう。「殺すつもりはありませんでした」という発話を受け入れることによって他の命題の真偽性を考えるのではなく、我々は三人称的な視点の事柄によって意図の存在を証明しようと試みるのであります。法において我々は、一人称において語るしかないような事柄を用いる正当化の様式を排除して解釈を行なっているのだ、このこと、すなわち論証における普遍化可能性の要求という点に法における解釈の特殊性を求めることができると思われます。
これを、ドゥオーキンの法理論におけるもうひとつの回答として定位することが可能であると思われます。彼は次のように述べています。「法というものは、(……)個別的なルールとか原理の目録に尽きるわけではない。(……)法の帝国は態度によって定義付けられるのであり、領域とか権限とか手続によって定義付けられるものではない」。我々の論証から一人称特権に基づく正当化を排除していくという法の性質は、このような運動としての法の定義として理解することが可能であろうと思われます。
残された課題
このような定位は、現に存在する法文を位置付けることに何ら寄与しないという批判があろうかと思います。私はしかしここで、第一に法文は運動としての法によって生み出されたいわば堆積物であり、それを単独で法と呼ぶことはできないということ、第二に法文はあくまで、繰り返し行なわれる法的論証の過程によって参照さるべき枠組としての位置を与えられることによってのみ法文としての位置を獲得するのであって、運動としての法の存在から独立に法としての性格が存在すると考えることはできないことから、あくまで法の中心は運動にあるのだと考えています。
一方ここで、すべてを三人称的視点で描写することを求める運動としての法を実効あらしめるための道具として、誰にとっても第三人称の位置に立つような存在としての法を考えることができます。それは理論的存在者として、さまざまな行為がその存在を前提として記述されることによって存在することになるでしょう。やや愉快な言い方をすればそれは、法人としての法ということになります。ドゥオーキンの「純一性としての法」の観念、すなわち井上達夫が「歴史的に持続する全体としての社会を、正しい原理を希求する一つの意志の支配の下に服せしめんとする企て」と呼ぶものはまさにそのような理論的存在者としての法であり、運動としての法によってその存在が措定される存在として理解することが可能であろうかと思います。しかしこの問題をさらに追求するためには、この私が何かを別の私として、すなわち理由を与えあう言語ゲームの参加者として認めることに関する研究が必要とされるでしょう。この問題に関しては、かつて実存的エゴイズムに関してその端緒を試みたのですがなお拡充が必要であると考えており、残念ながら本稿においては論点として取り扱うことができませんでした。この点に関しては、従って、問題点としての指摘にとどめておきます。
以上をもって発表を終えさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。
クリプキによる懐疑論的パラドックス
私が、過去に私が行なったことのない演算「68+57=125」を行なったと仮定しよう。これは容易な加法の計算であり、私はなんなくこれに正しい答を返すことができよう。だがクリプキは、この明確な規則遂行に対して疑問を呈する懐疑論者を登場させる。彼によれば私はプラスという言葉で加算ではなく「クワス算」を意味していたというのだ。ここで、クワス算は以下のような規則で与えられる。
x+yにおいて、その双方が57未満であれば加算と同じ答を与える。いずれか一方でも57以上の場合は、「5」を答として与える。
従って懐疑論者によれば、この場合私が答えるべき解は「5」だったということになる。我々はこの懐疑論者にどのように反論することができるだろうか。いくつかの反論の例について以下で検討しよう。
第一に、私は過去に同様の演算を行なっており、従って私はそのときと同じ規則に従っていると主張する方法が考えられる。しかしここで、「68+57」はそれ自体を私が過去に行なったことのない演算であると仮定されていたのであった。従って、過去に存在するまったく同じ例を引用することによって、それと同じ行為を私は行なったのだと主張することはできない。一方、過去の類似の例(例えば68+56)を挙げた場合、懐疑論者はその違いの部分に何らかの違いを見出だすような演算規則を主張するだろう。
第二に、規則の概念に訴える可能性が存在するだろう。すなわち、過去に与えられたのは一連の行動の指示であり事例ではなかったと主張するのである。x+yの加算において私は、まず1からx回カウントし、引き続きy回カウントする。だがやはり事態は改善しない。そこで存在したとされる規則について、同様の懐疑——例えば、私は過去にカウントによってクワウントを意味していたのだ——を提示することができるからである。
第三に、傾向性(disposition)による議論を考えることができる。規則によって私の内部に、ある条件の下で特定の行動を取るような態度が形成される。これが傾向性である。私はその傾向性に導かれて、今まで行なったことのない演算を今までと同様に行なうことができる。
しかしクリプキによれば、この議論は事実を記述することはできるが、正当性を供給することができない。仮に、「a+b=?」というパネル(a, bは任意の自然数とする)を見ると「5」と書き入れるチンパンジーを想像しよう。このチンパンジーは問題に反応する傾向性を習得していると考えることができるが、それは少なくとも我々が「プラス」という演算において期待する傾向性ではない。では、どのようにして主体が習得した傾向性があるべき傾向性と一致していることが知られ得るのか。あるいは、ある落語を聞くとその場にいたほとんど全員が笑い出すとしよう。ここで共同体(あるいはその場にいた全員)にある傾向性が存在すると考えることは可能だが、この問題は規則とは何の関係もない。
第四に、単純性に関する議論に訴えることが考えられる。ある主体の行動は、複数の仮説によって説明することができるだろう。そこで我々としては、想定される仮説のうちもっとも単純なものを便宜的に採用するのだと主張するのだ。しかし、この記述にすでに明らかな通り、単純性は可能な複数の仮説から一つを選択する際に用いられる基準である。だが懐疑論的パラドックスは過去の事実と仮説との関係をいかにしてとり結ぶことができるかという点に向けられているので、単純性のような規準が働く前提を崩してしまう。そこでは、可能な仮説が無限に広がってしまうのである。従って、この議論でパラドックスを無効化することはできない。この議論は他の規準による仮説選択に拡張することができる。仮説の選択に関する理論では、クリプキに対する答えにはならないのである。
結論的に、私はこの懐疑論者に対して私が特定の規則に従っていたことを立証する事実を示すことができず、従ってそのことを正当化することができない。
(助手論文 1.2.1.節をもとに再構成)
ルイス・キャロルによるアキレスと亀のパラドックス
限定的規約主義者であるアキレスが、亀に次のような推論を示したとする。
亀は足の回転が遅く、かつ頭の回転も遅い。……(1)
∴ 亀は頭の回転が遅い。……(2)
亀が反問する——「(1)を認めても、(2)を認めなかったら、どうします?」。アキレスは当然ながら(1)を認めた者は(2)を認めなくてはならないと主張するが、その根拠をさらに問われた場合には(a)それは直接的規約である(我々の取り決めとして記述されている) (b)それは派生的規約である のいずれかをもって答えなくてはならない。
しかし、上記(1)→(2)の導出を直接に定めた規約も、それを派生的に導く規約も見当たらないので、アキレスは次の規約をノートに書き込むことになる。
(1)から(2)が出て来なくてはならない。……(3)
しかし亀はさらにこのように問う——「(1)と(3)を認めて、それでも(2)を認めなかったら、どうします?」。同様のやりとりののち、アキレスは次の(4)をノートに記入することになる。
(1)と(3)から(2)が出て来なくてはならない。……(4)
以下同様に、いつまでたっても亀は納得せず、アキレスは規約をノートに書き込み続けることになる。
(野矢茂樹「根元的規約主義: 論証の生きる場としての論理」の設例より)
事態はアキレスにとってかなり悲観的である。いくつかの前提γから論理的にZを帰結するとき、それが「論理的」であること、すなわち前提γから結論Zが帰結せねばならないということを、限定的規約主義はγからZが導出されるような推論規則Rの取り決めによって説明しようとする。だがそのとき、規約Rもまた結論Zを帰結するための前提のひとつにすぎないものとなってしまう。そしてそれゆえ、こんどは前提「γ+R」から結論Zが帰結せねばならないことを説明しなければならなくなる。推論規則を規約として取り出したとたんに、それは前提へと組み込まれ、前提から結論への論理の道筋そのものは相変わらず積み残されてしまうのである。
(野矢茂樹『哲学・航海日誌』p. 133)
クリプキの懐疑的解決
ある人がある事を意味している、という言明を正当化するのに必要なものの全ては、
1. その言明が正当に行なわれ得るところの、大まかにでも特定し得る状況が存在し、
2. そのような状況の下でその言明が行なわれる言語ゲームが、我々の生活の中である役割を有している、ということである。
(ソール・A・クリプキ『ウィトゲンシュタインのパラドックス』pp. 77--78、邦訳 p. 151)
我々はほとんど皆、「68+57」は幾つかと問われたとき、何の躊躇もなく「125」と答え、プラスではなくクワスふうな規則が適切であったかもしれない、という理論的可能性について思いを致すことなどはしない。しかも我々はその計算を正当化なしに行なうのである。勿論、なぜ「125」と言うのか、と問われれば、我々はたいてい言うであろう。8と7をたして15を得、5を書いて1を繰り上げ、……と。しかし、もしその時、なぜ我々はそのように「繰り上げ」るのか、と問われれば、我々は何と言うであろうか。我々は過去において、「繰り上げ(carry)」は「クワリー(quarry)」を意味し、「クワリー」とは、……、ということを意図してはいなかったのか。懐疑的議論の核心は、我々は究極的には——我々の行為を正当化し得る——如何なる理由もなしに行為するレベルにまで至る、という事である。我々は躊躇なしに、しかし盲目的に行為するのである。
この計算の場合は、ウィトゲンシュタインが、「正当化」(Rechtfertigung)なしの、しかし「不当に」(zu Unrecht)ではない言語使用、と言う場合の重要な一例である。計算者は、究極的には如何なる正当化も与えることなく、ああする(例えば「5」と答える)よりもこうする(例えば「125」と答える)方が正しいのだという彼自身の確信に満ちた心の傾きに従ってよいという事は、規則について語る我々の言語ゲームの一部なのである。即ち、ある人に『この場合、私はこの規則にああではなくこう従うべきなのである。』と言うことを許す「言明可能性条件」は、究極的には、彼はああするよりもこうする方が正しいのだという彼自身の確信に満ちた心の傾きに従っているという事なのである。
(同 p. 87、邦訳 pp. 170--171)
二つの懐疑論
いま、ある立場xからある命題yを疑い得ることをFxyと表記するとき、個々の主張は以下のように対比される。
|
全面的懐疑論
|
簡単な言語的記述
すべての命題を疑うことのできるある立場が存在する
論理式による表現
∃x ∀y Fxy |
|---|---|
|
無限定的懐疑論
|
簡単な言語的記述
すべての命題に対して、それを疑うことのできる立場が存在する
論理式による表現
∀y ∃x Fxy |
(助手論文 1.2.4.節をもとに構成)
否定主導語(trouser-word)
「本当の」という言葉の主導権を握っている(wear the trousers)のは否定的用法なのである。すなわち、あるものが本当のものである、本当のこれこれである、という主張に一定の意味が与えられるのは、どういう場合にそれが本当のものではない、あるいはなかったとされうるのかが特定されることによってでしかない。(……)この事実こそ、「本当の」と呼ばれ、またそう呼ばれうるすべてのものに共通する特徴を見出そうとする試みが、きまって失敗する理由なのである。「本当の」という言葉の機能は、何かを肯定的に特徴づけることではなく、本当でない可能なあり方を排除することにある。
(J. L. Austin, Sense and Sensibilia, p. 70)
ここで事細かに規定されているのは、すべて異常の諸タイプなのである。それゆえ、私はむしろこう言いたくなる。——「正常な状態」などという状態は存在しない、あるのは異常な状態とその欠如のみでしかない。異常に関してはさまざまな観点からさまざまなチェックが為されるだろう。そしてそのように規定されたさまざまなタイプの「異常」が、その欠如としての「正常」を意味づける。「異常」が「正常」からの逸脱として規定されるのではなく、「正常」が「異常」の欠如として規定されるのである。まさに、「正常」という語は典型的な否定主導語にほかならない。
(野矢茂樹『心と他者』p. 49)
提出した論文の目次は以下の通り。
序論・法的判断の領域
0.0.1. 法的な判断の位置
0.0.2. 井上達夫の法命題概念
0.0.2.1. 法命題の定位
0.0.2.2. ウィトゲンシュタインの「石工の言語」
0.0.2.3. 遂行分析による考察
0.0.2.4. 導出の問題
0.0.3. 本稿の構成
第1章 哲学的基礎理論
1.1. 命法の指図性
1.1.1. 行動主義と情緒説
1.1.2. 言語行為論
1.2. 規則に従うこと—規則のパラドックス
1.2.1. クリプキの「懐疑論的パラドックス」
1.2.1.1. 根拠となる事実の候補
1.2.2. 懐疑論的パラドックスの射程
1.2.2.1. 井上達夫の定位とその失敗
1.2.2.2. ビックスの二分法とその失敗
1.2.3. クリプキの「懐疑論的解決」とその検討
1.2.3.1. ウィトゲンシュタイン理解としてのクリプキ
1.2.3.2. クリプキの「懐疑的解決」
1.2.3.3. 懐疑的解決の問題点
1.2.3.4. 懐疑論的パラドックスの前提
1.2.4. 二つの懐疑論
1.2.4.1. 懐疑論と生活形式
1.2.4.2. 河床の循環性
1.2.4.3. メタ論理的言明の改訂不可能性
1.3. 根元的規約主義
1.3.1. キャロルのパラドックス
1.3.2. 論証による意味制作
1.3.3. 正当性に関するデカルト的地平
1.3.3.1. 否定主導語としての「正常」
1.3.3.2. 日常言語ゲームと言語習得ゲーム
1.3.4. 意味の制作
1.3.4.1. 意味制作のモデル
1.3.4.2. 言語と実践的能力
1.4. 小結・事実命題と規範性
1.4.1. 補論・私と我々のあいだ
第2章 法解釈という営為
2.1. 解釈における意味—ドゥウォーキンとフィッシュ
2.1.1. ドゥウォーキンの構成的解釈
2.1.1.1. 解釈の類型論
2.1.1.2. 解釈と導出の関係
2.1.2. 構成的解釈の諸問題
2.1.2.1. テクストの選択と変更
2.1.2.2. 整合性の独立性
2.1.2.3. 「最善」の意味
2.1.3. フィッシュの解釈共同体理論
2.1.3.1. 解釈共同体理論の目的
2.1.3.2. 説得としての議論
2.1.3.3. フィッシュのドゥウォーキン批判
2.1.4. 解釈共同体理論の諸問題
2.1.4.1. 解釈共同体像の変遷
2.1.4.2. 解釈を選択する基準
2.1.4.3. 基礎付け関係と懐疑論
2.1.5. 解釈理論の諸問題
2.1.5.1. 導出の不確定性
2.1.5.2. 対審構造の必要性
2.2. 実践における探究—パターソンとヤブロン
2.2.1. ヤブロンの懐疑的解決
2.2.1.1. ドゥウォーキンのプラグマティズム像批判
2.2.1.2. 法における懐疑的解決
2.2.2. パターソンの様式理論
2.2.3. 実践理論の諸問題
2.2.3.1. 法的議論の必要性
2.2.3.2. 法全体の正当化
2.2.3.3. 論証と様式の一致
2.3. 意味の制作理論
2.3.0.1. 裁判制度の意味
2.3.0.2. 物語りとしての解釈
2.3.0.3. 三人称的記述としての法
第3章 結論—補足と展望
3.0.1. 自由とコミュニケーション
3.0.2. 批判可能性の問題
3.0.3. 運動としての法
3.0.4. 説得のゲーム
 HOME
HOME